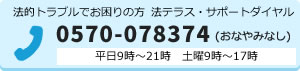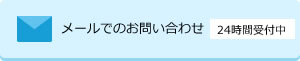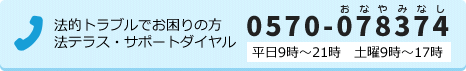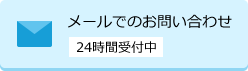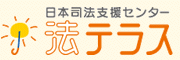Vol.8 滝鼻 卓雄さん
更新日:2018年6月28日
聞き手 法テラス理事 篠塚 英子

東大安田講堂裁判で始まった司法記者時代
- ―
- 滝鼻さんは1963年に読売新聞に入社されて司法担当記者もされていたとうかがっていますが、当時の司法界の様子はいかがでしたか。
- 滝鼻
- 私の司法記者としてのスタートは東大安田講堂事件の裁判でした。司法担当になる前から事件の取材をしていたので、社会部のデスクに「被告人といっしょに裁判所に行け!」と、送り込まれた感じでした。
- ―
- 被告人が多すぎて個人では間に合わず、グループ単位で裁判が行われたんですよね。
- 滝鼻
- 被告人が裁判に出廷しない、弁護人が裁判の途中で姿を消してしまうという異常事態のなか、被告人不在のまま判決が言い渡されました。その欠席裁判が合憲か違憲かも争われ、裁判所も弁護士も検察官も全員が戸惑っていたと思います。
- ―
- あれだけの騒ぎになったのは初めてでしたからね。
- 滝鼻
- この裁判で私は刑事訴訟法をかなり勉強しました。結局欠席裁判でも合憲という判断が下されましたが、弁護士が自ら退廷してしまうことに対しては、私は違和感を覚えました。本当に被告人の利益が守られたのかなと。一方、当時の裁判所は今より自由闊達な空気があったように思うんです。私の司法記者としての基本方針は、関係者すべてに直接取材するということでした。刑事事件なら被告人、被害者、検事、弁護士、そして裁判官。裁判官が一番難しかったですね。取材することには何の違法性もないんですが、裁判官が新聞記者と直接会おうとはしない。
- ―
- それでもあきらめなかったのですね。
- 滝鼻
- 裁判官は難しい言葉を使うでしょう。それで裁判官に「わからないまま報道していいのか」とつめ寄ると、「じゃあ、いらっしゃい」と会って解説してくれた。ところが、今の記者たちに聞くと、なかなか会ってくれないんだそうです。私は記者の力不足だって言ってるんですが(笑)。
- ―
- 司法記者はどのくらい務められたのですか。
- 滝鼻
- 結局12年現場にいましたね。それで、やり残したことがひとつあるんです。それは最高裁判所のインサイド・ストーリーがうまく書けなかったこと。70年代から80年代、私たちは「揺れる司法」と呼んでいましたが、公務員の政治活動や労働問題で最高裁の判断基準が動いた時代でした。そのときの裁判官はどう考え、どう評議していたのか。そんな最高裁の内幕を最後のライフワークとして書きたいと思っています。
正義の実現は国民の責任 裁判員制度で自覚を促す
- ―
- そのような時代を経て、司法制度改革が大詰めを迎え、裁判員制度がいよいよスタートします。この制度についてはどのようにお考えですか。
- 滝鼻
- 制度に関しては、肯定的な考えを持っています。国会に参考人として呼ばれた際にもそのような意見を申し上げました。国民の意識が高まっているか、十分理解されているかなど、不安な面もありますが、国民と司法の距離を縮め、国民の司法参加を促進するという意味では、いい制度だと思います。しかし、できあがった制度を見て、予想外だったことが2つあります。ひとつは6対3という構成の問題。
- ―
- 民間の裁判員が6名、プロの裁判官が3名の点ですね。
- 滝鼻
- 民間人は倍くらいいなければプロの裁判官と対等に議論できないだろうという判断だったのでしょうか。今でも民間人が多い気がします。もうひとつは裁判員が量刑まで関わるということです。量刑を決める評議に裁判員が参加することは果たしていいのか。国民がいちばん戸惑うところだと思います。
- ―
- そのような国民の意識と制度のギャップは、メディアの情報によっても変わってくると思います。メディアの役割は重大ですね。
- 滝鼻
- 日本では明治以来、「正義の実現」はお上の仕事だと考えられてきました。だからほとんどの裁判は職業裁判官が裁いてきた。「正義の実現の責任は国民にある」という自覚が育っていないんです。
- ―
- 「与えられた正義」ですね。
- 滝鼻
- 裁判員になることは法律上の義務になっています。正義を実現するために働くんだという自覚を作れるか。その役割の一端はメディアが担うことになるのでしょうね。
- ―
- 裁判員制度が始まることで、新聞の紙面づくりは変わりますか。記者の数を増やすとか。
- 滝鼻
- 裁判記事の扱いは基本的に変わらないでしょう。第1号の裁判は相当大きな記事になるでしょうし、各事件での裁判員の選考過程にもニュース価値があると思います。それを興味本位にならない範囲でどこまで伝えられるか。それは記者の数より質、記者の取材力にかかっていると思います。
知名度アップのためには人が集まる場所でPRを
- ―
- 法テラスも設立から4年目を迎えようとしています。身近な相談窓口としてもっと気軽にご利用いただくために、何が不足していると思われますか。
- 滝鼻
- 先日コールセンターを見学させていただき、非常にいい雰囲気で緊張感ある仕事をされているなと感じました。新聞社にも読者センターがあるので、お互いに情報交換したらいいとセンター長に伝えました。このように気軽に相談できるところがあるのだから、紛争の解決をアウトロー(無法者)に委ねる昔の日本の悪しき習慣はすぐに改めるべきですね。
- ―
- そのために津々浦々まで法テラスの存在を周知させることが、今の課題です。
- 滝鼻
- 2008年2月、巨人軍の宮崎キャンプに行ったとき、宮崎地検の検事正が来て、「キャンプ地にテントを張らせてほしい」と言うんです。裁判員制度のPRをしたいのだけど、地検にはそのための予算が十分ではない。だから毎日一万数千人が集まる宮崎キャンプでPRしたいと。けっこう効果はあったみたいですよ。
- ―
- いいお話ですね。
- 滝鼻
- 認知度を高めるためには人の集まるところでPRするべきです。新聞記事や広告も必要ですが、法テラスが外に出ていくことで司法と国民の距離を縮められると思うんです。
- ―
- 実は今年1月2日に、東京ドームで行われたマスターズリーグでチラシを配らせていただいたんですよ。
- 滝鼻
- いいところに目をつけましたね。検察庁とか裁判所とか、人が避けて通りたいところでPRしていたってだめですから(笑)。
- ―
- 本日は興味深いお話をいただき、ありがとうございました。
プロフィール

滝鼻 卓雄さん
1939年、東京都出身
慶応義塾大学法学部卒。1963年、読売新聞社に入社。1985年、論説委員。法務室長、社会部長、総務局長などを経て2004年1月、東京本社代表取締役社長兼編集主幹に就任。同年8月から読売巨人軍取締役オーナーを兼任。2007年6月より東京本社代表取締役会長に。
2008年10月、日本司法支援センター顧問に就任。