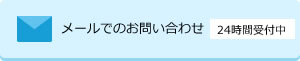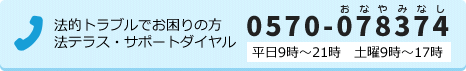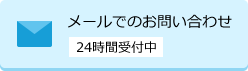家事:認知、養育費、面会交流、相続など
更新日:2023年7月6日
ご利用前にご一読ください。
- FAQは、日本の一般的な法制度を紹介するものであり、個別具体的な相談に対する答えではありません。また、個別の事情によっては、日本の法制度が適用されない場合があります。
- ここに掲載していないFAQがあるか知りたい方や、個別具体的な相談をなさりたい方は、多言語情報提供サービス(0570-08377)にお問合せください。相談内容に応じてFAQや相談窓口をお調べして、ご案内します。
- FAQに基づき、個別具体的なトラブルを解決しようとし、何らかの損害が生じた場合でも法テラスでは責任を負いかねますので、ご了承ください。
目次
認知
家族の問題
養育費
面会交流
相続
Q01: 認知の訴えとは何ですか?
![]()
- 父が認知に応じない場合に、家庭裁判所の判決により認知を認める手続です。
(説明)
・認知の訴えは、嫡出でない子及びその直系卑属(子や孫)が提起することができます。
・相手方が生きている限り訴訟を提起する前に必ず、家庭裁判所に認知調停を申し立てなくてはなりません。当事者の調停での合意が整っても直ちに認知が認められるわけではなく、家庭裁判所で事実を調査し合意を相当と認める場合のみに「合意に相当する審判」が行われ、これにより認知が認められます。
・調停で合意が成立しない場合にはじめて、認知の訴えを家庭裁判所に提起することになります。
・認知の訴えは父の生存中はいつでも可能ですが、死亡後は死後3年以内にしなくてはなりません。
・訴訟において、父と子の血縁関係が証明された場合には、認知を認める判決が言い渡されます。
・なお、胎児の場合、母が父を相手方として調停(胎児認知の届出を求める調停)を申し立てることはできますが、調停が不成立となった場合には、出生後でなければ認知の訴えを提起することはできないと解されています。
Q02: 法律上の婚姻関係にない日本人の父と外国人の母との間に生まれた子は、日本国籍を取得することができますか?
![]()
- 母が懐胎している間(生まれる前)に父が認知していれば、生まれた時から当然に日本国籍を取得します。
- 法定の要件を満たす場合には、届け出によって日本国籍を取得できます。
- 届け出による国籍取得が認められない場合でも、帰化の申請は可能です。
(説明)
・法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子(婚外子)は、日本国民である父が出生前に認知していれば、生まれた時から日本国籍を取得します。
・婚外子は、次の法定要件をすべて満たす場合には、国籍取得届を提出すれば日本国籍を取得できます。
(1)届け出の時に18歳未満(※)であること
(2)認知した父が、子が生まれた時に日本国民であること
(3)認知した父が、届け出の時に日本国民であること(父が届け出前に死亡しているときは、死亡した時に日本国民であったこと)
・国籍取得届は、日本に住所がある場合には住所地を管轄する法務局又は地方法務局、海外に住所がある場合には日本国の在外公館に提出します。
・詳しくは、法務局、地方法務局又は弁護士等の専門家に相談するとよいでしょう。
(※)2022年4月1日から、(1)の条件が20歳未満から18歳未満に変更しました。ただし、2024年3月31日まで、2022年4月1日時点で上記(2)と(3)の条件を満たしており、届出時に20歳未満であれば、国籍取得の届出をすることが可能です。
Q03: 既婚者と不倫をしたところ、不倫相手の配偶者から慰謝料を請求されました。この請求は認められるのでしょうか?
![]()
- 原則として慰謝料の請求は認められます。ただし、不倫相手の結婚生活が、不倫関係が始まった時点で実体を失っていたと認められる場合や不倫相手が婚姻していることを十分な注意をしても知ることができず、真実を知らなかった場合には、慰謝料の請求は認められないものと思われます。
(説明)
・既婚者と不倫する行為は、不倫相手の配偶者に対する不法行為となりますので、慰謝料支払義務が発生することとなります。
・ただし、不倫関係が始まった時点で、不倫相手とその配偶者の結婚生活が既に実体を失っていたような場合には、慰謝料の請求は認められないと考えられます。
・これは、法的に保護に値する婚姻の実体関係が失われているという考えに基づきます。
・また、そもそも相手方が婚姻していることを十分な注意をしていても知ることができず(不倫の相手方である既婚者が独身であるとだましていたなど)、真実を知らなかった場合には、結果として婚姻生活への侵害をしたことになっても、故意や過失がないことから不法行為は成立せず、慰謝料請求は認められないと考えられます。
Q04: 私は日本人ですが、外国籍の子を養子にすることができますか?
![]()
- 日本の民法は養子となる者の国籍を問いませんので、外国籍の子を養子にすることもできます。
- もっとも、外国にいる外国籍の子を養子にしても、その養子に対して当然に日本における在留資格が認められるわけではありませんので、注意する必要があります。
(説明)
・養子縁組は、縁組の当時における「養親となるべき者」の本国法によりますので、日本人が養親となるときは、日本の民法に基づいて判断されます。もっとも、「養子となるべき者」の本国法に養子の保護要件(例えば、本人や第三者の承諾、公的機関の許可など)の定めがあれば、その保護要件を備えることも必要です。
・養子縁組の成立に裁判所の関与が必要とされる場合(例えば、未成年者を養子とする場合や、特別養子縁組をする場合)に、養親となるべき者か、養子となるべき者のいずれか一方(または双方)が日本に住んでいれば、日本の家庭裁判所を利用することができます。
・外国籍の子について、以下の場合には、原則として日本における在留資格が認められます。
(1) 日本人の特別養子であれば、在留資格「日本人の配偶者等」
(2) 日本人である養親に扶養される6歳未満の普通養子であれば、在留資格「定住者」
(3) 中国残留邦人の養子(ただし、6歳に達する前から引き続き養親となる者と同居して扶養を受けている等の条件あり)であれば、在留資格「定住者」
・6歳以上の普通養子であっても、その養子が、「日本人の配偶者等」の在留資格で在留する外国人に扶養される未成年で未婚の実子であれば、その外国人の連れ子として、在留資格「定住者」が認められる場合があります。
・詳しくは、弁護士等の専門家にご相談なさってください。なお、関係する外国の弁護士等に相談することが必要な場合もありますので、その確認も含めてご相談なさることをお勧めいたします。
Q05: 離婚時に養育費の取決めをしなかったのですが、離婚後しばらく経ってからでも、子どもの養育費の支払いを受けることができますか?その際、過去分の養育費の支払いを受けることはできますか?
![]()
- 子が扶養を必要とする状態にある限り、離婚後においても養育費を請求することができます。
- 過去分の養育費の支払義務が認められる場合もありますが、養育費についての協議ができない場合や協議が調わない場合にどこまでさかのぼって認められるかは裁判所の判断となります。実務上は請求したとき以降の部分に限られることが多いようです。
(説明)
・養育費の支払義務は、親権や同居の有無とはかかわりなく、親子という関係そのものに基づいて発生する義務です。離婚後であっても子が要扶養状態にある限り、父母は養育費を分担する義務を負います。
・養育費の取り決めをせずに離婚をした場合には、父母の協議によって、支払額、支払時期、支払方法等を決定することになります。この場合、子の利益を最も優先的に考慮しなければなりません。
・協議ができない場合や協議が調わない場合には、家庭裁判所に養育費支払いの調停・審判を求めることになります。過去分の養育費を請求した場合、家庭裁判所は、過去分をどれだけさかのぼるかも含めて、養育費に関する決定を行います。
・養育費について、具体的に支払時期や金額が決められているときは、養育費の請求権は、支払時期から5年の経過により、時効によって消滅します。しかし、何らの取り決めもない場合の過去分の養育費は、消滅時効の対象にはなりません。
・詳しくは、弁護士に相談するとよいでしょう。
Q06: 養育費の取決めをしましたが、支払が滞っています。法的にどのような手段がありますか?
![]()
- 調停や審判等によって取り決めをした場合には、履行勧告、履行命令、強制執行があります。
- 強制執行認諾文言付公正証書によって取り決めをした場合には、強制執行があります。
(説明)
・口頭や当事者間で作成した書類の取り決めだけでは、支払いを法的に強制することはできません。この場合には家庭裁判所に養育費の支払いを求める調停を申し立てる方法があります。
・すでに家庭裁判所で調停や審判等がなされている場合には、その取り決めに従った養育費の支払確保の手段として、家庭裁判所に申し立てる履行勧告・履行命令、及び地方裁判所に申し立てる強制執行があります。公証役場において強制執行認諾文言付公正証書を作成した場合には、強制執行のみ利用できます。
・履行勧告・履行命令の手続については、調停・審判等をした家庭裁判所にご確認ください。強制執行の手続きについては、相手方の住所地を管轄する地方裁判所(不動産の強制執行については、その所在地を管轄する地方裁判所)にご確認ください。
・いずれの方法を選択すべきかや、その時期など、具体的事例に即した判断については、弁護士に相談することをお勧めします。
Q07: 養育費の減額を請求することができますか?
![]()
- 養育費の額が決められた当時に予測し得なかった個人的、社会的事情の変更が生じ、現在の養育費の額では実情に合わなくなった場合には、養育費の減額を請求することができます。
(説明)
・扶養の程度または方法は、扶養の必要性、扶養義務者の経済力その他一切の事情を考慮して定められるものです。
・いったん取り決められたり、審判で認められたりした養育費であっても、その後の父母の経済状態に変動があったり、養育費が増加したりするなど、予想されていなかった事情の変更があった場合には、家庭裁判所は、養育費の変更または取消しをすることができます。
・養育費の額が決められた当時でも、ある程度予測される範囲内での状況の変化は、養育費の額を変更すべき事情の変更とは認められません。
・養育費の額が決められた当時に予測できなかった状況の変化としては、親の勤務する会社の倒産による失業、親の病気やケガによる長期入院、親が再婚した場合の再婚後の家庭のための生活費の増加等が考えられます。
・以上のような状況の変化がある場合には、それが養育費の額を変更すべき事情の変更に当たるとして、父母の協議または調停、審判によって、養育費の減額を請求することができます。
・子が他の人の養子となった場合には、養親が第一次的な養育費の支払義務を負担することになりますので、減額請求が認められる可能性があります。
・詳しくは、弁護士等の専門家に相談するとよいでしょう。
Q08: 子との面会交流をしたいのですが、どうすればいいですか?
![]()
- 父母の離婚後または別居中の、子との面会交流に関することは、父母の話し合いで決めることになります。話し合いがうまくいかない場合や、約束どおりに面会交流をさせてもらえない場合には、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。
(説明)
・子との面会交流については、親の権利という視点ではなく、子の利益を最も優先して、子の負担にならないよう、子の福祉につながる配慮が必要です。
・面会交流の方法は、頻度、時間、場所などを、できるだけ具体的に決めておくようにします。
・話し合いがうまくいかない場合や、約束どおりに面会交流をさせてもらえない場合には、家庭裁判所に面会交流の調停を申し立てることができます。調停が不成立となったときは、自動的に審判手続が開始され、裁判官が、一切の事情を考慮して、面会交流の方法などを決める審判(子の監護に関する処分)をします。
・詳しくは、弁護士に相談するとよいでしょう。
※国際的な結婚生活が破綻した際、一方の親がもう一方の親の同意を得ることなく、子を自分の母国へ連れ出すという「子の連れ去り」が行われると、子にとってそれまでの生活基盤が突然急変し、子に有害な影響を与える可能性があります。この問題については、ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)に関するFAQもご確認ください。
Q09: 元配偶者が養育費を払いません。養育費を払わない元配偶者でも面会交流をさせなければならないのですか?
![]()
- 養育費の支払いと面会交流の実施は、対価関係にありません。したがって、「養育費の支払いがないから面会交流をさせない」あるいは「面会交流をさせてくれないから養育費を支払わない」といった主張は認められません。
- もっとも、正当な理由もないのに養育費の支払いをしない場合は、面会交流が制限される可能性があります。
(説明)
・養育費の支払いと面会交流の実施は、いずれも子の健全な生育のために必要不可欠なものです。両者は、いわゆる「対価関係」になく、一方が実現しない間は他方も実現しなくてよい、といったことにはなりません。
・したがって、「養育費を支払わない元配偶者とは面会交流をさせない」あるいは「面会交流をさせてくれない元配偶者には養育費を支払わない」といった主張は認められません。
・しかし、経済的な余裕があるにもかかわらず養育費を支払わないなど、正当な理由なく養育費の支払いをしない場合については、面会交流を制限すべきだとする見解もあります。養育費を支払うという、親としての重要な責任を果たさないでおきながら、面会交流を求めることを、一種の権利濫用と評価することがあります。
・詳しくは、弁護士にご相談なさってください。
Q10: 法定相続人とは何ですか?
![]()
- 民法で相続人となることができると定められた相続人を、法定相続人といいます。
(説明)
・法定相続人には、配偶者と血族の2種類があります。
・配偶者は、常に相続人となります。
・血族には順位がついており、先順位の者が相続人となります。
・第1順位は、被相続人の子です。子が死亡しているときは、その代襲者(子、孫、ひ孫等)です。
・第2順位は、直系尊属(被相続人の親等)です。
・第3順位は、被相続人の兄弟姉妹です。兄弟姉妹が死亡しているときは、その代襲者(子のみに限られ、孫、ひ孫等は含まれません)です。
Q11: 遺産分割の手続には、どのようなものがありますか?
![]()
- 次の4つの手続があります。
1. 遺言による遺産分割
2. 相続人同士の協議による遺産分割
3. 家庭裁判所の調停による遺産分割
4. 家庭裁判所の審判による遺産分割
(説明)
・遺産分割は、共同相続した遺産を各相続人に分割する手続です。
・遺産及び相続人の範囲は、相続の開始によって初めて確定するため、相続開始後における各相続人の合意によって成立した協議でなければ効力を生じないものとされています。そのため、相続開始前(被相続人の存命中)の遺産分割協議は無効です。
・遺産分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各相続人は、家庭裁判所に調停申立てあるいは審判の申立てをすることができます。
・調停とは、調停委員等を介した話合いにより分割方法を決定する手続です。
・審判とは、裁判所により、強制的に遺産分割の方法を決定する手続です。
・初めから審判の申立てをすることもできますが、まずは審判に先立ち、調停の申立てをすることが一般的です。
・調停の申立ては、相手方(共同相続人の1人)の住所地または当事者が合意で定める家庭裁判所に対して行います。
・審判の申立ては、相続開始地(被相続人の最後の住所地)を管轄する家庭裁判所または当事者が合意で定める家庭裁判所に対して行います。
Q12: 死亡した者の遺言書を見つけました。相続手続はどうしたらよいでしょうか?
![]()
- 家庭裁判所に対し、遺言の検認の申立てをする必要があります。
- 遺言の内容によっては、遺言執行者の選任が必要な場合もあります。
(説明)
・公正証書によって作成された遺言を除いては、遺言書の保管者が相続の開始を知ったとき、または遺言書を発見した相続人は、速やかに家庭裁判所に提出し、その検認を請求する必要があります。
・特に不動産の相続登記をしたい場合は、公正証書によって作成された遺言を除いては、家庭裁判所の検認を受けていなければ、登記の添付書類として利用できません。
・なお、法務局における遺言書の保管等に関する法律(遺言書保管法)の施行日(2020年7月10日)以後に、この法律に基づいて法務局に保管された遺言も、検認を受ける必要はありません。
・検認は、遺言書の検証をするだけであり、遺言内容の真否などその効力を判断するものではありません。したがって、遺言内容の有効性、無効性については、裁判などで争うこととなります。
・財産の遺贈や推定相続人の廃除、認知という遺言の内容を実現するには、遺言執行者の行為が必要です。遺言に遺言執行者が定められていない場合には、家庭裁判所に遺言執行者の選任を請求することとなります。
Q13: 相続放棄とはどのような手続ですか?
![]()
- 相続人が、被相続人の権利義務の承継を拒否する意思表示であり、家庭裁判所での手続です。
(説明)
・相続放棄は、相続が開始したことを知ってから3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書を提出し、それが受理されることによって認められます。なお、形式的に受理されても相続放棄の有効が確定するものではなく、法律上の無効原因などがある場合は、後でその有効性を訴訟で争うことも可能と解されています。
・3か月以内で判断がつかないときには、家庭裁判所に期間の伸長の申立てができます。
・相続開始後しばらくしてから債権者の請求を受け、そのときに初めて被相続人の債務の存在を知ったような場合には、相続開始後3か月を経過していても、相続放棄が認められる場合があります。
・相続放棄すると、その者は最初から相続人でなかったことになります。放棄者の直系卑属(子、孫など)に代襲相続が起きることもありません。
・相続放棄により、法定相続における後順位の者が相続人となります。たとえば すべての子が相続放棄をすると、直系尊属(父母等)が相続人となります。さらに全ての直系尊属が相続放棄をすると、兄弟姉妹が相続人となります。また、被相続人の配偶者は常に相続人となります。
・相続財産が債務超過の場合、債務を免れるためには、これらの者全てが相続放棄をする必要があります。
Q14: 相続放棄は、いつまでに行えばよいのですか?
![]()
- 自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内です。なお、この期間は「熟慮期間」と呼ばれています。
(説明)
・「自分のために相続の開始があったことを知った時」とは、被相続人(亡くなられた人)の死亡の事実を知った時です。ただし、先順位者の相続放棄によって相続人となる場合(例えば、被相続人の子が相続放棄をしたことで、被相続人の父母が相続人となる場合)は、先順位者の相続放棄についても知った時です。
・熟慮期間内に、相続放棄の申述書を、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。家庭裁判所で申述書が受理されると、相続放棄が認められます。
・相続人が複数いる場合には、3か月の熟慮期間は各人別々に進行します。
・相続人本人のほか、利害関係人(例えば、相続人の債権者、次順位の相続人、被相続人の債権者や債務者)からの請求により、この3か月の熟慮期間は延長されることがあります。
・なお、「自分のために相続の開始があったことを知った時」から3か月を経過してしまった場合でも、例外的に相続放棄の申述が認められることもあります。
・借金などの負債を含めて、相続財産が全く存在しないと信じ、そのように信じることに相当な理由がある場合には、3か月の熟慮期間は、相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時か、通常認識し得る時から起算すべき、とする最高裁判所の判例があります。
Q15: 日本に長年在住した外国人が日本に財産を遺(のこ)して亡くなりました。相続の手続はどのように進めることになるのですか?
![]()
- 被相続人である外国人が亡くなった時に日本に住んでいた場合は、日本の裁判所(家庭裁判所)で手続を進めることもできます。
- 原則として、被相続人である外国人の本国法に基づいて判断しますが、日本法(日本の民法)に基づいて判断することになる場合もあります。
(説明)
・「どこの国の裁判所で手続を進めることができるか」という国際裁判管轄の問題と、「どこの国の法に基づいて判断するか」という準拠法の問題があります。
≪国際裁判管轄≫
・相続放棄については、被相続人が亡くなった時に日本に住んでいた場合には、日本の裁判所(家庭裁判所)に管轄が認められます。
・遺産分割については、被相続人が亡くなった時に日本に住んでいた場合のほか、相続人が日本の裁判所で遺産分割を行う旨の合意をした場合にも、日本の裁判所(家庭裁判所)に管轄が認められます。
・もっとも、外国にも遺産が存在する場合に、日本で成立した遺産分割調停や審判に基づいて、外国で執行できるのかといった問題もあります。日本の裁判所(家庭裁判所)で遺産分割の手続を進めることが適切かどうか、慎重に検討しておく必要があります。
≪準拠法≫
・日本の国際私法(法の適用に関する通則法)では、「相続は、被相続人の本国法による」とされており、準拠法は被相続人である外国人の本国法となります。 例えば、亡くなった外国人が韓国籍であれば、原則として、韓国法(韓国の民法)が準拠法となります。
・もっとも、被相続人の本国の国際私法で異なる定めがなされていて、日本法(日本の民法)が準拠法となることもあります。例えば、中国の国際私法(渉外民事関係法律適用法)では、「不動産の法定相続については、不動産の所在地法を適用する」とされており、中国籍の外国人が遺言を作成しないで亡くなった場合に、遺産として日本にある不動産の相続に関しては、日本法(日本の民法)が準拠法となります。
・以上のように、国際的な要素を含む相続の問題は複雑ですので、弁護士等の専門家にご相談なさってください。関係する外国の弁護士等に相談することが必要な場合もありますので、その確認を含めてご相談なさることをお勧めいたします。
Q16: 私は外国人ですが、一昨年、日本人配偶者と結婚し2人で暮らしていました。日本での生活にも慣れ、幸せに暮らしていましたが、先日、配偶者が突然亡くなりました。現在の在留資格は「日本人の配偶者等」です。このまま日本で暮らすことができますか?
![]()
- 同居人や親族の方が死亡した場合、亡くなった日から7日以内に市区町村に死亡届を提出しなければなりません。
- 加えて、日本人の配偶者と死別した場合、あなたは「日本人の配偶者等」でなくなりますから、14日以内に、地方出入国在留管理官署に届け出なければなりません。
- これからも日本で暮らしたいのであれば、配偶者が亡くなってから6か月以内に、在留資格を満たしていると思われる在留資格への変更をする必要があります。
(説明)
・「日本人の配偶者等」の在留資格により在留する外国人が日本人配偶者と死別した場合、配偶者が亡くなった日から14日以内に、地方出入国在留管理署への出頭又は東京出入国在留管理局への郵送により法務大臣に届出が必要です。これを怠ると、在留資格を喪失してしまう危険もありますので、注意が必要です。
・日本に在留し続けるには、その後、6か月以内に、在留資格変更の手続をとらなければなりません。
・日本で生活している年数が長く(婚姻期間が3年以上など)、生活基盤もしっかりしていれば在留資格を「定住者」に変更できる場合がありますが、今回のケースの場合、日本での生活が3年未満と短いため、在留資格を変更して日本に住み続けることは難しいと思われます。
・ただし、亡くなった夫との間に子どもがいて扶養の必要があるなど一定の要件を満たした場合には、「定住者」の在留資格への変更が許可されることになっています。
・その他、やむを得ない事情がある場合は、出入国在留管理局にご相談ください。